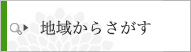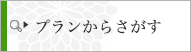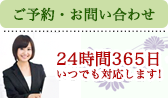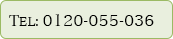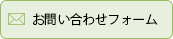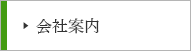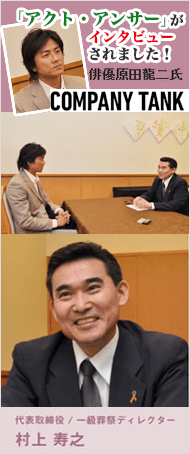飾り輿とは、葬儀に使用される白木(生花)祭壇の一番上に飾ってある輿の事です。
輿には、本輿(柩を納める事が出来る)、半輿(柩を納める事が出来ない)飾り輿があります。
歴史としては、平安時代に天皇、皇后などに限られ二本の轅(ながえ)に屋形を乗せて人を運ぶ乗り物として出来ました。これは、お神輿(神様を乗せて担ぐ物)を真似てできたようです。
昔、輿は葬儀の時に葬列を組んで埋葬の為に墓地へと向かう時に柩を納めて担ぐ物で、平安時代中期頃に始まりましたが、位の高い人たちだけで、庶民レベルには全く浸透していませんでした。
また、日本の葬儀史の資料も少ない為、諸説ありますが、江戸後期には、棺も形が変り、庶民も輿を担いで葬列を組んで墓地まで運ぶ儀式が始まったそうです。
形だけで心のこもっていない、意味のない儀礼は止めよう、という意味です。
昭和20年代後半から30年代にかけては、全国各地で新生活運動が展開され「虚礼廃止」の名の下で葬儀の香典、香典返し、花環などの廃止、自粛、制限が広まり、自治体による公営葬儀も出現するようになりました。
一般的には、年賀状や、贈賄に繋がる政治家への中元などについて言う場合が多いようです。
建物の縁,須弥壇などの端にある手すり・欄干のことです。勾欄とも書きます。
地覆 (じふく) 、平桁 (ひらげた) 、架木 (ほこぎ) の3つの水平材から成るものです。
架木の先端がまっすぐなものを組高欄、そり上がっているものを刎 (はね) 高欄、隅あるいは端に擬宝珠 (ぎぼし) 柱を立てたものを擬宝珠高欄と言います。
仏堂の須弥檀(しゅみだん)の前に香炉などの「三具足」や「五具足」を置く机のことです。
また、仏前に置き、経を読むときに使う経机のことでもあります。
祭壇とは、葬儀式に用いられる壇をいいます。遺影写真や供物を飾り、故人を偲び供養します。
仏式の葬儀の場合は、祭壇の前には経机が置かれて、お坊さんが読経をします。
伝統的に、白木祭壇が用いられてきましたが、近年、花祭壇を選ばれる方も増えています。
キリスト教の場合は、お花を飾り十字架を設置します。
神式の場合は、祭壇には神饌物(しんせんもの)や幣帛(へいはく)など、神道の儀式にならったお供えものを飾ります。
遺体を納めた「柩(ひつぎ)」を運ぶための車のことを言います。
高級乗用車やステーションワゴンなどを改造したものが多く用いられております。
そして車の形から宮型、バン型 (洋型)、バス型などがあります。
死者を火葬場や埋葬場まで、遺族・親族を初め一般会葬者も参加して、つき従って送ること言います。
また、その行列のことを言いました。
現代では近代化し、火葬場までは、主な関係者が、霊枢車に従いハイヤーに分乗して行く場合が多くなりました。
それでも辺境の町村では、まだこの「野辺送り」を行なっているところもあります。
座棺とは、遺体を座った姿勢で納めるように作った棺のことです。
また、寝棺(ねかん)とは、遺体をあおむけに寝かせたまま納めるように作った棺のことです。
「ねがん」とも言います。
明治政府は仏教での葬法としての火葬に反対した神道派の主張を受け入れ、1873年(明治6年)7月18日太政官布告により出された布告が「火葬禁止令」です。
しかし、仏教徒の反発が強く、また衛生面からも火葬が好ましいとの意見もあり、さらに都市部での土葬スペース不足という現実には逆らえず、約2年後の1875年(明治8年)5月23日に火葬禁止令が解除されました。[
火葬(かそう)とは、葬送の一手段として遺体を焼却することです。
また、遺体の焼却を行う葬儀自体を指すこともあります。(火葬式)
そして、その火葬を行う施設や建築物を火葬場(かそうば)と呼びます。



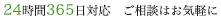
 HOME
HOME