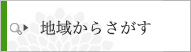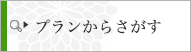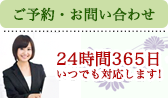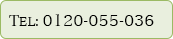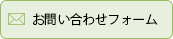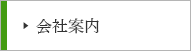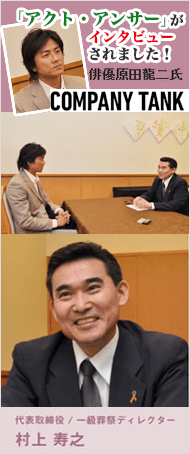本日(8/9日)は、八千代市の東葉高速線八千代中央駅の南口方向にある斎場より、千葉市斎場にて火葬の「家族葬」の施行を対応いたしました。
リピーターである喪家様からは「前回は亡くなった翌日に通夜~葬儀とすぐに送ってしまい、ゆっくりお別れが出来なかったので、今回は時間に余裕を持って送りたい…」と言うご希望でしたので今回は、お別れする時間に余裕を持たせる為の葬儀日程をご提案いたしましたので「今回はゆっくりお別れが出来ました、ありがとうございました」と、大変お喜びいただきました。
当社は、お客様に合ったプランをご提供致しますので、絶対に後悔をさせません!!
何なりとご相談下さいませ!!
「お盆」のお布施
お盆法要のお布施:5,000円~1万円
お盆の時期には、菩提寺のお坊さんが檀家の家をまわり読経をあげます。棚経とも言います。自宅でお経をあげてもらったら、お布施を渡すことが多いです。
新盆・初盆(故人が亡くなりはじめて迎えるお盆)のときには、親戚にも声をかけて盛大に初盆法要を執り行うため、お布施は3万円~5万円前後を目安として渡すことがあります。
また、家に来てもらう場合、5,000円~1万円をお車代として用意したり、食事会(お斎)に出席してもらったり、食事代を別で渡したりすることもあります。
「お彼岸」のお布施
個別法要のお布施:3万円~5万円
合同法要会のお布施:3,000円~1万円
春・秋と2回あるお彼岸の時期にお寺にお経をあげて供養をしてもらった時にお布施を渡します。
お彼岸法要では、お寺で行われる合同のお彼岸法要に参加したり、個別でお寺にお彼岸法要を依頼したりと様々です。
「法事法要」のお布施の費用相場としては
祥月命日法要のお布施:5,000円~1万円程度
四十九日法要のお布施:3万円~5万円程度
一周忌法要のお布施 :3万円~5万円程度
三回忌以降のお布施 :1万円~5万円程度
法事法要では僧侶に読経をあげてもらい、供養してもらったお礼も込めてお布施を渡すことが多いです。
四十九日法要や一周忌など、特に重要とされている法事法要のお布施は、祥月命日の法要などのお布施よりも気持ち多めにお金を包むことがあります。 また、葬儀の際にお渡ししたお布施の「一割くらい」とも言われています。(お寺様とのお付き合いの深さにもよります)
また、お寺の本堂ではなく、法要のために式場や自宅にお寺を呼ぶ場合、お布施とは別に、お車代(5,000円~1万円)を渡すこともあります。
「納骨時」のお布施の金額
お墓や納骨堂に遺骨を納骨する、納骨法要・納骨式のときには、お布施は1万円~5万円くらいといわれています。
「お墓を改葬する時」のお布施の相場
閉眼供養・魂抜きのお布施:1万円~5万円
開眼供養・魂入れのお布施:1万円~5万円
菩提寺の墓地にお墓があるときには、上記以外に「離檀料」が必要な場合があります。
お通夜、葬儀・告別式にお寺の僧侶を呼んだ場合に、供養をしてもらった御礼としてお布施を渡します。
その目安としては
東京近郊のお布施:およそ20万円~35万円
大阪近郊のお布施:およそ20万円前後
お布施の費用は、約15万円~50万円といった範囲が多いようです。(二日間のお葬儀で戒名や読経をお願いした場合)
菩提寺がなくて、葬儀社などに紹介してもらったお寺の場合は、事前に「お布施(宗教者への謝礼)は○○万円くらいです」とお布施の金額を伝えられますので葬儀社に確認してからお願いしましょう。
ただし、お布施は地域や各お寺の考え方、お寺との付き合いの深さによっても変わるものです。お布施の価値は人それぞれ異なるため、自分が包める金額で相談することが大切です。
本日(5日)は、船橋市の馬込町に在る公営斎場(夏見の運動公園の北に位置)、また同じ敷地内に火葬場も隣接の「馬込斎場の保管室」より「火葬式」の施行を対応いたしました。
喪家様からは「とにかく費用を抑えたいので・・・」とのご希望でした。そこで当社は、喪家様のご要望の予算に合わせる為、最も費用を抑えられる火葬式をご提案いたしました。
また、ご自宅には故人様をご安置が出来ない・・・との事でしたので、当社の保管室(関連施設)と公営斎場の馬込斎場の保管室にご安置いたしました。
喪家様からは「おかげで費用も抑えられ、支払いに関しても特別なご対応を戴き、ありがとうございました・・・」と、大変お喜びいただきました。
当社は、お客様に合ったプランをご提供致しますので、絶対に後悔をさせません!!
何なりとご相談下さいませ!!
お布施(布施)とは、僧侶へ読経や戒名を頂いた謝礼として金品を渡すことをいいます。または、本尊へお供えするという考え方をとります。
読経や戒名の対価という意味ではないので、読経料や戒名料という言葉は使いませんのでご注意ください。
お布施を渡す時は、半紙に包むか、白封筒に入れ水引は掛けません。「御布施」と表書きをするか何も書かなくてもよいとされています。また、相手に不幸があったわけではないですので、不祝儀袋(黒い水引の袋)は使用しません。
お渡しする際は直接ではなく、お盆に乗せる形が好ましいです。
お布施は気持ちでお渡しするものであり決まった金額というのはありません。各お寺様ごとに考え方もありますので、よく分からないという場合は、直接お伺いすることがよいでしょう。
本日(3日)は、船橋市の馬込町に在る公営斎場(夏見の運動公園の北に位置)、また同じ敷地内に火葬場も隣接の「馬込斎場」より「家族葬」の施行を対応いたしました。
喪家様からは「当初は火葬式で送ろうとしていましたが、後悔をしたくないので最低限での葬儀で送りたいです。またお花の祭壇を飾りたい・・・」とのご希望でした。そこで当社は、喪家様のご要望の予算に合わせる為、まずは費用をかなり抑えられるように「市民葬」プランを適応した家族葬で、更に特別価格での生花祭壇プランをご提案いたしました。
また、ご自宅には故人様をご安置が出来ない・・・との事でしたので、当社の保管室(関連施設)と公営斎場の馬込斎場の保管室にご安置いたしました。
喪家様からは「おかげで費用も抑えられ、きちんとした葬儀で心残りなく送ることができ、ありがとうございました・・・」と、大変お喜びいただきました。
当社は、お客様に合ったプランをご提供致しますので、絶対に後悔をさせません!!
何なりとご相談下さいませ!!
本日(8/2日)は、松戸市の東武鉄道野田線(東武アーバンパークライン)六実駅の西口にある斎場より、松戸市斎場にて火葬の「家族葬」の施行を対応いたしました。
喪家様からは「古式湯灌をお願いしたことで、大変穏やかで安らかな故人になり心残りなく送ることができました。また、火葬終了後に式場に戻ってからの精進落としでも会場が無料でお借りでき、ありがとうございました・・・」と、
また、「お花の祭壇で立派にしたい・・」と言うご希望でしたので、きれいなお花の祭壇を飾るプランでの施行をご提案しましたので、大変お喜びいただきました。
当社は、お客様に合ったプランをご提供致しますので、絶対に後悔をさせません!!
何なりとご相談下さいませ!!
位号とは、戒名の下に付けられる「居士・大姉」などの文字のことであり、性別や年齢、功徳報恩や社会功績などにより異なります。
「居士・大姉」は、強い信仰を持った信者に贈られます。
「信士・信女」は、仏教信者として五戒や十善戒を保つ成人の男女に対して付けられます。
成人とする年齢については、諸説がありますが、18歳以上とするのが一般的です。宗派により、清士・清女、清浄士・清浄女、善士・善女などとなっています。 江戸時代は武士以上に対して居士・大姉を付け、庶民に対しては信士・信女を付けたと言われていますが、武士階級でも信士・信女が付いている場合もあり全くの俗説です。
「童子・童女」は、未成年の内に亡くなった剃髪・得度をしていない者に対して付けられます。
未成年とする年齢についても、諸説がありますが、18歳未満、4、5歳から17歳に付けるのが一般的です。宗派により、大童子・大童女、清童子・清童女、禅童子・禅童女などとなっています。
幼児の場合では、2、3歳には「孩子・孩女」、0、1歳には「嬰子・嬰女」が付けられます。
「水子」は、死産や乳児の頃に夭折した者に対して付けられます。
正しくは「すいし」または「すいじ」と読みますが、近年は「みずこ」と読むことが多くなっています。
「禪尼・禅尼」は、曹洞宗の住職夫人あるいは未亡人の戒名につけられる位号です。
位号を用いない宗旨としては、律宗・浄土真宗が相当します。
しかし、地域の慣習により位号を付けることもありますが、宗門として認められた形式ではありません。
本日(31日)は、松戸市の東武鉄道野田線(東武アーバンパークライン)六実駅の西口にある斎場にて、「お別れ会(骨葬)」の施行を対応いたしました。
喪家様(代表者はご友人)からは「特に式次第などは必要ありません。とにかく親しい友人だけが集まってお別れ会をしたいのです。その場所を提供してほしいのでお願いします・・・」との事でした。
結果として、お通夜~告別式と同様な時間を設定し、一晩ゆっくりと故人様とお過ごしいただきました。
喪家様(代表者はご友人)からは「故人とゆっくりお別れが出来、心残りなく送ることができました。また、費用もかなり抑えていただき、ありがとうございました・・・」と、大変お喜びいただきました。
当社は、お客様に合ったプランをご提供致しますので、絶対に後悔をさせません!!
何なりとご相談下さいませ!!



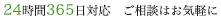
 HOME
HOME