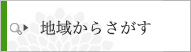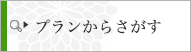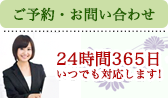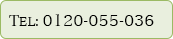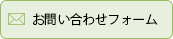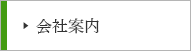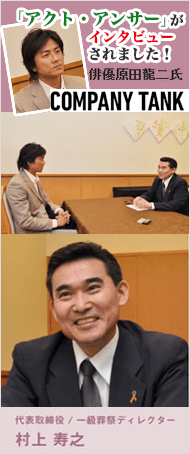本日(21日)は、成田市の吉倉に在る公営斎場(JR成田駅から約3Kmに位置)、また同じ敷地内に火葬場も隣接の「八富成田斎場」にて「一日葬」の施行を対応いたしました。
喪家様からは「故人は横浜に在住していて、亡くなったのも横浜、しかし現在横浜には故人以外はいないので自分が現在住んでいる成田市で葬儀を出したい。また出来るだけ費用も抑えたい・・」とのご希望でしたので、公営斎場の「八富成田斎場」での「一日葬」をご提案いたしました。
また、警察扱いでもあり、ご自宅にはお帰りになれないという事で、公営斎場の「八富成田斎場」の安置室に警察から直接ご安置出来るように手配をさせて頂きました。喪家様からは「おかげで費用も抑えられ、スムースに送ることができ、ありがとうございました・・・」と、大変お喜びいただきました。
当社は、お客様に合ったプランをご提供致しますので、絶対に後悔をさせません!!
何なりとご相談下さいませ!!
司法解剖(しほうかいぼう)とは、犯罪性のある死体またはその疑いのある死体の死因などを究明するために行われる解剖です。
刑事訴訟法168条1項「鑑定人による死体の解剖」、同法229条「検視」、および死体解剖保存法の規定に基づいて、刑事事件の処理を目的に行われます。
多くのケースでは被解剖者の遺族への心情的配慮から、その了承を得た上で解剖が行われていますが、法律上は裁判所から「鑑定処分許可状」の発行を受ければ、遺族の同意が得られなくても職権で強制的に行うことが可能です。
現状としては、予算や医師不足などの理由から、警察の死体取扱い件数のほとんどが司法解剖されていません。また、同様の事情により変死と思われるような状況でも、自殺や事故、心不全で片付けられることもあるともいわれています。打開策としてオートプシー・イメージングが提案されていますが、運用のための法案等システムが未だ整っていません。
行政解剖(ぎょうせいかいぼう)とは、死体解剖保存法に基づいて主に監察医が行う解剖のことを言います。
主に死因の判明しない犯罪性のない異状死体に対して、死因の究明を目的として行われる解剖です。
検視または検案によって犯罪性があると認められた場合は、刑事訴訟法に基づいて司法解剖となります。
狭義の行政解剖は、死体解剖保存法8条に基づき、都道府県知事が設置する監察医が行う死体解剖を指します。この場合、死体解剖保存法7条3号、同法2条1項3号の規定により遺族の承諾は必要とされません。監察医が置かれるのは、「監察医を置くべき地域を定める政令(昭和24年12月9日政令第385号)」により、東京23区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市となっています。
広義の行政解剖は、死体解剖保存法2条1項に基づき行われる死体解剖の内、司法解剖、病理解剖を除いたものを言いますが、法律上は、病理解剖と広義の行政解剖の間には明確な線引きはありません。解剖を行うのが監察医に限らない点が狭義の行政解剖と異なります。広義の行政解剖のうち、(1)狭義の行政解剖、(2)食品衛生法59条2項の規定による解剖、(3)検疫法13条2項後段の規定に該当する解剖以外は、死体解剖保存法7条により遺族の承諾が必要です。(ただし、遺族の所在が不明な場合などでは例外があります。)監察医を置いていない地域では、県警察本部が「行政解剖実施要綱」を定めているケースが多くありす。
死体検案書(したいけんあんしょ)とは、死亡事由などについての検案について記した書類のことです。
死亡診断書と同等に死亡を証明する効力を持つもので、検案した医師のみが死体検案書を発行できます。
死亡診断書と異なり、歯科医師は死体検案書を発行できません。
死亡診断書と死体検案書の様式は同一のものです。(死因統計作成の資料としても用いられます。)
死因が継続的に診療中のものである場合については死亡診断書が作成されます。それ以外の場合は死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければなりません。検案によって異状死(異状死体参照)であると判断した場合は、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならなくなります。その後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回される事になります。
医師が死亡を確認した後、その証明書として発行するのが「死亡診断書」です。
死亡診断書には、死亡者の氏名・性別・生年月日や、死亡時刻・死亡場所・死因・手術の有無などが書かれています。
※ 通常、生命保険の請求などにも添付書類として必要です。
用紙は多くの場合医師が持っています。もし無い場合は、役所の戸籍係の窓口に死亡届と合わせて一枚になった用紙が置いてあります。
※ 用紙そのものはコピーでもよく、死亡届と二枚に分かれても構いません。
医師に必要事項を記入していただきそれを受け取ってください。一番下に医師名を書く欄がありますので、ペンによる自筆のサインか、ゴム印・印刷・コピー・カーボンコピーの名前に医師の名前の印(認印可)を押印していることを確認してください。
※ 自筆のサインの場合は押印は無くても有効です。病院の印は必要ありません。
注意!
死亡診断書が発行されるのは「自然死」「死因の明確な死」の場合です。事故・自殺・突然死・原因不明の死などの場合、監察医や警察委託の医師による検案の後「死体検案書」が発行されます。(内容項目は大差ありません)
行政に死亡を届け出る書類が「死亡届」です。
届け出ができるのは、以下の3ヵ所の市区町村に限られています。
・死亡地
・死亡者の本籍地
・届出人の住所地
※ 「死亡者の住所地」がダメなことに注意!
届け出る窓口は、本庁・支所・出張所(サービスセンター)の戸籍の係です。
※ 「市民課戸籍係」など、名称はそれぞれです。
原則として24時間365日提出できますが、ほとんどの役所では休日や夜間の受付を守衛さんに委託していますので、守衛さんのいない出張所などでは業務時間内にしか提出できません。
手続きに持って行くのは、以下のものです。
・死亡届
・死亡診断書 (原本は還りませんので、コピーを取っておくことををお奨めします。)
・届出人の認印
なお、届け出は原則として「死亡を知った日から7日以内」と定められていますが、通常それまでに葬儀と火葬をしますので、火葬までに手続きをする必要があります。
死亡届には以下のような情報を記入します。
・死亡者の氏名・性別・生年月日
・死亡時刻と死亡場所 ※ 名称ではなく住所や施設所在地(死亡診断書に記載されています)
・死亡者の住所と本籍
・死亡者の配偶者の有無など
・死亡者の属する世帯の主な仕事(世帯主の職業分類) ※ 国勢調査の年には本人の職業・産業も
・届出人の住所と本籍
・届出人の氏名(署名)・生年月日
・火葬(または埋葬)の場所 ※ 使用する火葬場や墓地の名称
・予備的に、続柄や電話番号など
用紙は多くの場合医師から渡された死亡診断書と一枚になっています。 もし無い場合は、役所の戸籍係の窓口に置いてあります。
印鑑は届出人の認印で構いませんので、署名の後と欄外(「○文字修正」などと書いてある場所か、無ければスペースのあるところ)に押印します。現在では印がなくても受理されますが、まれに役所によっては嫌がるので押印した方が無難です。
本日(15日)は、船橋市の馬込町に在る公営斎場(夏見の運動公園の北に位置)、また同じ敷地内に火葬場も隣接の「馬込斎場」より「家族葬」の施行を対応いたしました。
喪家様からは「故人は、木材関係の仕事をしていたので「白木の祭壇」を飾ってあげたい・・」とのご希望でしたので、出来るだけ費用も抑えられるように「市民葬」で、白木の祭壇を飾るご提案いたしました。
また、ご自宅で亡くなった事もありましたので古式湯灌をご提案いたしました。更に、菩提寺様の都合により日程が延びましたので、お通夜の当日にお体の再処置を無料にてさせて頂きました。喪家様からは「おかげで最後までお顔の色も変わらず穏やかなお顔のままで、心残りなく送ることができ、ありがとうございました・・・」と、大変お喜びいただきました。
当社は、お客様に合ったプランをご提供致しますので、絶対に後悔をさせません!!
何なりとご相談下さいませ!!
ご遺体を火葬(または埋葬)するためには、役所に「死亡届け」を提出し、火葬(または埋葬)の許可を受ける必要があります。
その際に、発行される書類(許可書)が「火葬(埋葬)許可証」です。
この手続きは葬儀社が代行することが通例ですが、状況によってはご家族がしなければならない場合がありますので、葬儀社や役所にご確認してください。
本日(13日)は、松戸市の東武鉄道野田線(東武アーバンパークライン)六実駅の西口にある斎場より、ウイングホール柏斎場にて火葬の「家族葬」の施行を対応いたしました。
喪家様からは「シャワー湯灌をお願いしたことで、大変穏やかで安らかな故人になり心残りなく送ることができました。また、火葬終了後に式場に戻ってからの精進落としでも会場が無料でお借りでき、ありがとうございました・・・」と、
また、「お花の祭壇で立派にしたい・・」と言うご希望でしたので、きれいなお花の祭壇を飾るプランでの施行をご提案しましたので、大変お喜びいただきました。
当社は、お客様に合ったプランをご提供致しますので、絶対に後悔をさせません!!
何なりとご相談下さいませ!!
収骨とは、火葬後に箸で骨を拾うことを言います。
収骨の手順は次の通りです。
まず喪主様から近い順に二人ずつで大きい骨から箸で掴み、骨壷の中に収めます。
但し、宗派や地域の慣習により違いますので、火夫さん(火葬場の従業員)や宗教者の指示に従うことをお勧めいたします。
よく「お骨を二人でつかむのはなぜでしょう?」と尋ねられることがあります。これにはいろいろな説があります、
一、お釈迦様のお骨を弟子たちが取り合った・・・という説
一、故人を天国への橋(箸)渡し、という願いを込める意味からではないか・・・
一、二人で行なうことにより、悲しみを半減させる為・・・など、という説があるようです。
このように、箸と箸で食べ物をつかむという行為は、亡くなった時に行なう縁起の良いものではない事から「食事の時に、箸と箸で食べ物をつかむことは、やってはいけない・・」と現在でも言われております。
また、お骨に色がついている場合もありますが、これは火葬の高温により棺の中に納めたお花の色などがつくことがあるためです。病気や薬などが原因ではありません。着色は副葬品によるものです。
最後に「埋葬許可証」の説明があり、収骨容器と一緒に、箱の中入れられます。
これは埋葬するために必要なものですので、しっかり確認し覚えておきましょう。



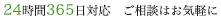
 HOME
HOME